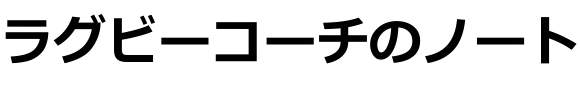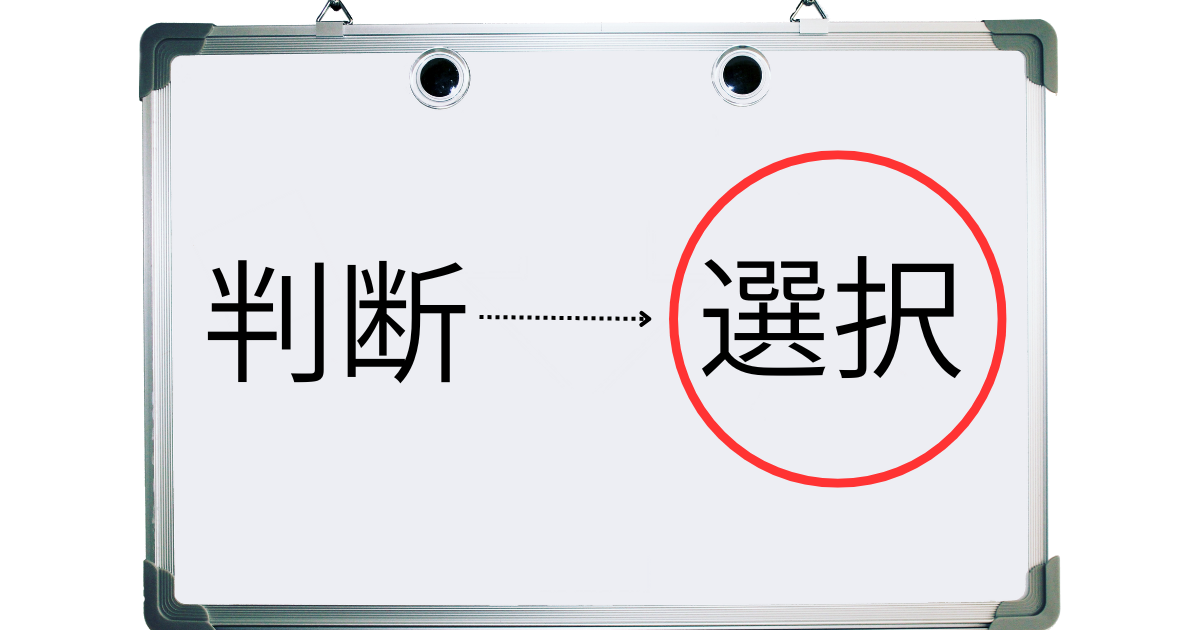「判断しろ!」
ラグビーのコーチング現場で、聞かない日はないんじゃないでしょうか。
本当によく聞きます。
この言葉を使ったことがない人はラグビー界にいないのでは…くらい。
もちろん、私も過去に使ったことはあります。
でも、今はもう使いません。
それはなぜか?
理由は、「判断」は、ラグビーの本質ではないからです。
確かに、「判断をする」「デシジョンメイキング(decision making)」などと言われ、ラグビーでは一般的に使われる言葉ですよね。
しかし、ラグビーのプレーにおいて行われるのは、正確には「判断」ではありません。
間違ってはいませんが、正確な表現ではないです。
正確に表現すると…
ある判断基準の中で、プレーを「選択」している。
ということです。
つまり、
ラグビーの本質はプレー選択にある。
このことを選手はもちろん、コーチが十分に理解し、指導に落とし込むことができるかが重要です。
今回のテーマは…
「判断」という言葉を使わず、「選択」という言葉を使ってコーチングしませんか?!
という提案です。
ちなみに私は、ほとんど「判断」という言葉は使いません。
その方がむしろ、コーチングもしやすいし、選手にとっても親切だからです。
【本記事でわかること】
・ラグビーの本質は「プレー選択」にあるという考え方
・コーチが「判断」という言葉を使わない4つの具体的な理由
※超重要※ラグビーの本質は「プレー選択」にある
ラグビーの本質は「プレー選択」にある。
冒頭にこのように表現しました。
なんとなくこの意味、理解できるでしょうか?
まずはこの意味を理解し、コーチングの出発点にして欲しいと思います。
ラグビーの試合では、刻一刻と変化する状況の中で、
選手が自らの意思で無数の「選択」を繰り返すことで成り立っています。
パス、ラン、キック、タックル、サポートなど、すべては選手がその瞬間に最善と考える「選択」の連続の結果と言えます。
どれだけ適切な「選択」を取れるかが、勝負の分かれ目になります。
ギリギリの状況下で行われる「選択」の駆け引きこそが、ラグビーをプレーする面白さだと思います。
ラグビーの試合は、まるで壮大なカードゲームのようなもの。
選手一人ひとりが、自分の手札にさまざまな「プレーのカード」を持っています。
パス、ラン、キック、タックル、ブレイクダウンへの参加、サポート…。
これらが、選手が繰り出せるカード…つまり「プレーの選択肢」です。
相手の状況、味方の位置、グラウンドのスペースや環境、そして時間や点差など…。
これら膨大な情報を瞬時に読み解きます。
そして、自分の手札の中から
「よし、今はこのパスのカードを切ろう!」
「ここはキャリーのカードだ!」
と、相手と駆け引きをしながら最適な「カード(プレー)」を選んで出し合っています。
よくカードゲームの例えを選手にもしています。
ラグビーの本質を伝える上で、理解しやすいからです。

ラグビーのプレーの本質は、まさにこの「選択」にある。
本質というものはシンプルです。
この考えが最も重要であり、大前提にあります。
「判断」という言葉を使わない理由4つ
「判断しろ!」
選手にはどのような意図が伝わっているでしょうか?
「判断」という言葉は、実はコーチが使う言葉としては、難しい言葉だと私は思っています。
だから私は使いません。
かわりに「選択」という言葉を使います。
それはなぜか。
まず【基礎編】では「判断」という言葉を使わない理由を4つを解説します。
1. 「正しい判断」を要求されるプレッシャー
「判断」という言葉には、「正しい判断」への要求が想起されます。
「正しい判断」はすなわち成功・正解です。
「正しい判断」への要求はハードルが高いです。
常に正解を当てていかないといけないプレッシャーがあるからです。
また「正しさ」というのは、状況や立場によって大きく異なります。
多くの場合、「コーチにとって正しい」と思う判断が選手に求められます。
しかし、選手にはその「正しさ」の基準が明確に伝わっていないことがあります。
つまり、コーチが持つ正解を当てないといけない、という不要なプレッシャーが選手にかかります。
2. 「間違った判断」が叱責の原因になる恐怖
「なんでそんな判断するんだ」
聞いたことありませんか?
選手が「間違った判断」をしたときにコーチがよく使う言葉です。
おそらくここから叱責が始まるんではないか…。
この恐怖ともいえる中で、選手がのびのびとプレーできるはずがありません。
間違った判断をすることへの恐れから、プレーが消極的になったり、思考が停止してしまったりするケースも少なくないです。
失敗を恐れるあまり、新しいことに挑戦したり、リスクを冒したりする意欲が失われてしまう可能性があります。
3. 「行動への指示」として曖昧な表現
「判断しろ!」
と言われても、
「じゃあ結局何をするの?」
という具体的な行動に繋がらないことがあります。
「判断」という言葉は意外にも曖昧な表現なのです。
選手は次のステップに進むためのヒントを得られず、思考がその場で止まってしまいます。
行動に落とし込まれないので、具体的な改善がされない可能性があります。
「判断しろ」と指示しても、それは選手の行動には反映されず、コーチの自己満足になる可能性が高いです。
4. 問いかけとして使いづらい言葉
「判断」という言葉はコーチからの「問いかけ」としても使いづらいです。
「なんでこの判断をしないんだ!」
とコーチから言われても選手は返答に困ります。
「だってそう判断したんだもん…いまさら言われても…」としか答えられないじゃないかと思います。
「対話」を促すための「問いかけ」としては物足りないです。
選手と「対話」するためには、「答えやすい問いかけ」をする必要があります。
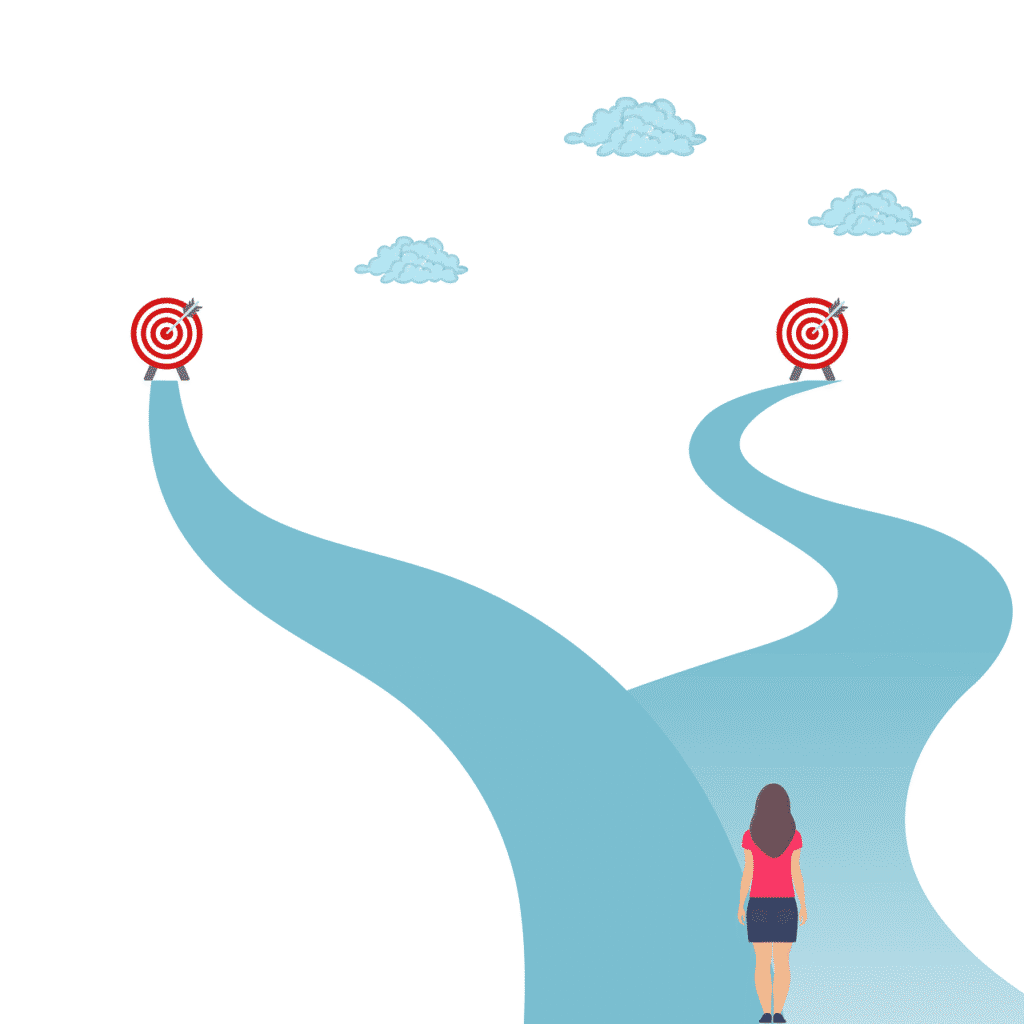
まとめ
まずは、ラグビーの本質が「プレー選択」にあることをご理解いただけたでしょうか。
コーチングをする上で、もっとも重要で前提部分となる考え方です。
またこの記事では、コーチが「判断」という言葉ではなく「選択」という言葉を使うべき理由の基礎を解説しました。
- ラグビーの本質は、刻一刻と変化する状況下での「プレー選択」の連続にある。
- 「判断」という言葉は、選手に不要なプレッシャーを与え、恐怖心や思考停止を招き、具体的な行動への指示としても曖昧であるため、コーチが使うには難しい。
※「判断」という言葉自体が悪いわけではありませんし、絶対に使ってはいけないなんてことはありません。
しかし、私たちが当たり前に使っている言葉が、選手にどのような影響を与えるのか…。
その特性を知ることが、より良いコーチングへの第一歩になります。
次の記事では、実際にコーチが「選択」という言葉を使うことで得られる具体的なメリットについて、さらに深掘りしていきます。